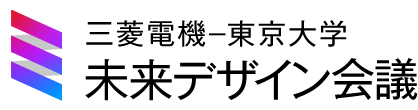研究課題 01 |
サーキュラーエコノミーの実現に向けて
持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座
研究課題 01 |
サーキュラーエコノミーの実現に向けて持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座
「見える化/定量化」がサーキュラーエコノミー実現の鍵を握る。研究を事業につなぐ“架け橋”への挑戦──三菱電機・執行航希 × 長澤忍 × 美寿見奈穂

従来の大量生産・大量消費を前提としたものづくりから、近年では欧州を中心に、資源循環を通した価値創出を目指すサーキュラーエコノミー(以下、CE)への移行が大きなトレンドとなっています。そうした潮流を受けて、2023年10月、三菱電機と東京大学は共同でCEの実現に向けた社会連携講座「持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座」を創設しました。
この講座では日本製造業の強みを活かして、CEの実現に向けた循環エコシステムの設計と検証、そして実現に向けた課題の抽出と解決に取り組んでいます。三菱電機のさまざまな事業・製品を実際の事例として検証しながら、その実現に向けた有効な手段を模索しています。
鍵を握るのは、「見える化/定量化」である──そう語るのは、本プロジェクトに三菱電機メンバーとして参加する情報技術総合研究所の執行航希さんと、先端技術総合研究所の長澤忍さん、そして本社リビング・デジタルマルチメディア事業本部の美寿見奈穂さんです。
講座では、CEの研究をどのように進め、どのように事業につなげていくことを考えているのでしょうか。本インタビューでは、社会連携講座に参画している三菱電機メンバ―の3人にお伺いしました。
サーキュラーエコノミーの実現に必要なものは何か?
──三菱電機と東京大学で開設した社会連携講座 「持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座」は、2023年10月の活動開始から約1年が経過しました。ここまでを振り返って、研究所メンバーのお二人はCEに対する考え方がどのように変わったかをお聞かせいただけますか?

執行 「サーキュラーエコノミー」という言葉を聞いて、多くの人は「原材料をリサイクルできればCEなんでしょう?」と漠然と理解していると思います。なぜなら、一年前に社会連携講座がはじまった時、僕も同じような認識だったからです。
だから、講座がはじまってすぐに「そうではない」と気付いた時は驚きでした。あくまでリサイクルは、CEを実現するための手段、一要素でしかない。本来のCEという概念は、複雑に関係しあうさまざまな構成要素を組み合わせて考えていくものだと知ったんです。
ひとつ例を挙げると、本講座では、既存事業に対して、“Narrow/Efficient/Slow/Close”の4つの観点から経済モデルを変える方法を検討しています。たとえば、「安い原材料でモノをつくって売る」という従来の生産工程に対して、「つくったものを有効活用する」という“Efficient”の発想を取り入れてみたり、原材料の投入量を少なくする“Narrow”を当てはめてみたりといったようにです。
このようにCEは想像以上に複雑なのですが、研究や理論から生まれたフレームワークをもとに、既存の事業モデルをどのように変えればCEの実現に近づくかを考えていく。それが僕たちの役割だといまは考えています。
──メーカーがCEを実現するためには何が重要になるとお考えでしょうか?
執行 まず重要なのは、「実際にどれくらいCEが実現されているのか」がわかるようにすること。言いかえれば、指標の設計や計測による「定量化」が大事だと思います。
きちんと実際の達成度を数値化し、可視化・評価していく。その先にCEを着実に事業などに実装していくことができるのではないかと考えています。

長澤 この定量化という話は、研究や理論をビジネスへと接続するという観点でも重要です。きちんとCEのメリットを数字で説明できるまで落とし込まなければ、事業部の方々が首を縦には振ってくれないからです。
私は研究所に所属しているのですが、CEを実装する理想的な方法は、「資源循環の取り組みに注力すると当社の経済活動にも旨味があります」と言えることだと思います。研究者や技術者が客観的で信憑性があるデータをきちんと用意し、事業部の方々にもわかるように説明してはじめて、「資源循環に取り組んでみよう」とビジネスが動き出すと思うんです。
だから、私たちは社内の人間、特に事業サイドの人間が安心して動けるようなデータを集めること。それを信じた方々が、きちんとビジネスがうまくいくようなデータを責任持って提言することが大事だと思うんです。
──続いて、事業部メンバーにも話を伺いたいと思います。美寿見さんは、社会連携講座から生まれた研究や知見を事業企画に活かす方法を考えていらっしゃるとお聞きしました。

美寿見 はい。私は現在家電製品やソリューションの実務担当として、販売店などを経由した「モノ売り」だけでない新規事業やサービスを考える部署に所属しています。三菱電機では全社的にCEの重要性が謳われはじめている中で、CEにつながるサービスを検討する機会もあって、この領域に興味を持ちました。
というのも、CEの実装には技術的な側面だけでなく、従来のメーカーの事業構造を大きく転換する必要があります。リユースやリファービッシュ(メーカー再生品・修理再生品)、サブスクリプションなど、新しいビジネスモデルを試行錯誤しなければならない。「どうすればCEを家電に応用して新しいビジネスを展開できるか?」といったことを検討する部隊もありますので、そうした方々のためにも、現在は社会連携講座で情報を集めています。
そして、研究所メンバーのお二人が話されていたように、定量化や数値化はやはり重要だと思います。事業部のメンバーにはまだまだ「CEってリサイクルのことだよね?」という認識不足はありますし、当然「本当にCEって儲かるの?」と疑問に思う人も少なくありません。まずはCEの正しい理解を伝えつつ、最終的にどうやって実現するか、どれくらいの効果が期待できるかを整理して事業部との橋渡しをすることが私の役割だと思っています。
CEを事業へと橋渡しする「エコシステムシミュレーター」
──結局はデータが大事であるとのことですが、具体的には社会連携講座に関連して、どのような研究や技術開発を進められているのでしょうか?
執行 現在、僕たち研究所メンバーが注力しているのが、「何が資源循環として再利用できるのか」を割り出せる「エコシステムシミュレーター」の開発です。
たとえば、三菱電機の各製品がどのような素材からできているのか。どれくらい分解しやすいのか。素材の再利用にどれくらいのコストがかかるのか。どれくらい環境負荷を低減できるのか……。こうした情報を収集して、製品設計を担当する方や、美寿見さんのような事業部の方々が新しい事業を検討する上で必要になる情報を出力できるようになる。そんな技術の開発を現在進めています。
長澤 私はそのシミュレーターにインプットするデータベースの作成や調査を担当しています。三菱電機には、冷蔵庫やエアコンなど家庭用機器から、電車のような大型機器まで、幅広い製品があります。それをできる限り抜け漏れなく分析できるようにデータを集め、CEのフレームワークとあわせて、どのような製品や事業を変えていくと、環境負荷を低減しつつ企業としての利益にもつながるかを調べています。
──執行さんは光技術部、長澤さんは電機システム技術部に所属とのことで、お二人とも「シミュレーター」からは少し専門性に距離があるように感じます。どのような経緯やモチベーションからCEに興味を持ったのでしょうか?

執行 現在、僕は光を用いた計測・測定をメインの業務にしています。これは大学院での研究の延長線上にありまして、もともとモノの3次元形状や、そのモノがどんな素材からできているのかを光技術で計測する方法を研究していたんです。
CEに興味を持ったのは、いまお話した「光で素材を識別したい」というモチベーションが原点です。僕は幼少期に北海道の小さな村に住んでいたことがあったのですが、大自然が豊かな反面、落ちているゴミが非常に目立つので、ゴミやモノを捨てることが嫌いだったんです。当時小学生だった僕はいつもゴミ拾いしながら歩いていて、ある時「そもそもなぜゴミ拾わなきゃいけないんだろう」という疑問を持ちました。そこで調べてわかった「生態系の中で分解されない素材だから」という知識が、CEに興味を持つ原点だったと思います。
その後、「光でモノを測る」という技術を通じて素材を選別し、結果的にモノを捨てずに有効活用する方法を模索するようになります。たとえば、人間は木から出来た製品を見たら「これは木だ」とわかります。ですが、それを光技術で計測することで判別し、有効活用が可能かどうかを判別できるようにならないだろうか。そんな研究に興味があり、気がついたらここにいました。
長澤 私は入社からずっと「電磁ノイズの対策」という少しニッチな分野を専門に仕事をしていました。自分の職掌の範囲で、かつもっと社会にわかりやすい形で貢献できる技術はないかと色々調べていたところ、CEと親和性が高い有価物の選別技術に応用できる可能性があることがわかったんです。
ただ、技術はたしかに大事なのですが、それだけではダメであるとも知りました。もっと重要なのは、そもそもどの製品に、どのような有価物が、どれだけ入ってるのかを見極めること。それがわかってはじめて、選別技術を活用した有価物回収の事業化につなげることができる。そのように考えたことが、シミュレーターにインプットするためのデータベースの作成という現在の業務につながっています。

事業化への道のりにある、乗り越えるべきハードル
──こうしたシミュレーターの開発が進めば、事業部としてもビジネスに応用しやすくなるのでしょうか?
美寿見 そう思います。特に社会連携講座が開発しているシミュレーターは、CEの資源循環という「サーキュラー」の側面だけでなく、それを事業や経済圏として成り立たせる「エコノミー」もきちんと考える点が面白いと思うんです。
まずは何が資源として再利用できるのかをシミュレーションする。そこから、実際にどのようにビジネスとして運用していくかを考えていく。事業を動かす側としても、情報が出揃うほど「やろう」と言いやすくなるので、シミュレーター開発にはとても期待しています。
──ただ、実際にビジネスの運用までを考えると、大変な仕事も少なくない気がします。

美寿見 たしかに実働を考えるとやるべきことが山積みです。リユースやリファービッシュを事業に取り入れるにあたって、製品の回収をどのようなオペレーションでやるか。回収してきたものをどうやって修理し、いかに売るのか。そういった運用面やスキームを考えるのは大変ですし、解決すべき課題だらけです。
従来の、新品を売り切る事業を行ってきたメーカーから、いかに体制や考え方を変えて資産の投資や回収をしていくか。事業計画の試算方法も変わりますし、全部が新しいチャレンジだと思います。
──今回の社会連携講座では、さまざまな業種の他社と協業しながらCEのエコシステムを構築していく、とも梅田先生はお話されていました。
美寿見:そうですね。とはいえ、最初は三菱電機の関連会社などの間でCEの実装を模索していくことになると思います。たとえば、保守や修理を専門とする関連会社がありますし、物流やロジスティクスサービスも専門の会社がある。まずはそうした“陣営”と呼ばれる関係性の中で、しっかりとビジネスをつくれるかどうかを目先では検証していきたいと思っています。
他方で、三菱電機やグループ会社だけでは限界もあります。たとえば、販売店や古物商ができるセカンドハンドのサービス事業者、レンタル業者などと連携、協力して、徐々にできることを拡大していくことは、中長期的には必要かもしれません。
執行:その点に関連して、いま未来デザイン会議の中で目指しているCEの理想像には、おそらく二つほどステージがあると思っていまして。一つ目が、既存のステークホルダーや、既存のシステムの中にCEの考え方を組み込み、いかに資源循環の度合いを向上させるかという視点です。
一方で、もっと深く「いま存在している経済のエコシステムを根底から変えていくためには?」という視点やアプローチも必要と思っています。このギャップをどのように埋めていくのかも同時並行で考えていく必要があるなと思います。

長澤 ただ、直近で難しいのは社内での足並みを揃えることだと感じています。三菱電機は全国各地に事業所があるため、情報共有などにギャップが生まれやすい構造があります。同じ拠点内であれば「情報をください」とお願いしやすいのですが、遠方の拠点となると物理的に距離が離れるとともに心の距離も離れてしまう。同じ三菱電機内でも、情報を共有しあうことが難しい課題があるんです。
本当は社会全体を巻き込んで一緒に連携するという視座で動くべきなのですが、まだまだ自社内ですら十分に意思疎通がしきれてない。他社との連携・協力を進めていくのなら、まずは自社内の足並みを揃えて連携できなければ始まりませんし、そこで躓いている場合でないですよね。そんなモチベーションを持ちながらも仕事をしています。
執行 それはとても同意します。ただ、三菱電機は貴重なデータが眠っている宝庫でもあるので、うまく活用できた時のインパクトは大きいはずです。そして、外部の力を活用して会社を変えていくこともひとつの手段だと思っていまして、この東京大学との連携はまさにその1つだと思います。このチャンスを有効に活かしていきたいと思っています。
三菱電機のイメージを刷新していくために
──ここまでの1年間を振り返りつつ、今後の社会連携講座に対する意気込みをお聞かせください。
長澤:まず正直にいうと、この1年間ですごくバシっとかっこいい成果が出たわけではありません。しかし、着実に手応えは得られていると感じます。
先ほどは「CEビジネスに転換するポテンシャルがある製品や事業を特定する」という話までしかしませんでしたが、最終的な私の目標は、責任と確信を持って「この事業や製品をCEに転換しましょう」という将来性のある提案をすることです。残りの2年間では、それをきちんとやりきりたい。データ上でただ特定するだけでなく、その先にある「どう変えたらいいのか」、どのような方法で一石を投じたらいいのかという事業提案までやれればと思っています。
執行:私も同じ気持ちです。そして、現在自分が手がけている計測技術の研究や開発を進めた先に、それが実現できるようになると信じています。
たとえば、製品を撮影するだけで、原材料や製造工程のボトルネック、物資輸送にかかるコストが算出できるようになること。「CO2排出量」など単一の指標だけでなく、CEの経済圏全体を複数のパラメーターでシミュレーションできるようにすること。これらができれば、人々の意識は一気に変わっていくと思いますし、これからも引き続きやっていきたいと思います。
美寿見:いまの社会連携講座のお話は、もともと家電開発に携わっていた私でも難しくて「ポカーン」としてしまうことがあります。このままではたぶん、事業部の皆さんも「?」となってしまうので、私は中間のパイプのような役割を担って、地道に“橋渡し”のような活動をしていければいいなと思っています。
長澤:近年急速に普及したQRコード決済のように、いずれは三菱電機発の「ニュースタンダード」を打ち出せたらいいですよね。5年後か10年後かはわかりませんが、いまは想像できないような仕組みを発明して、それが社会に広く浸透している。そんな新しい常識を、この社会連携講座が生み出すきっかけになったらいいなと思います。
美寿見:たしかに。三菱電機はたぶん、地味なイメージを持たれがちですよね。だからこそ、「三菱電機やってくれたな!」と言わせるようなモノやサービスをつくりたいですし、お客様からは「三菱電機の製品やサービスなら安心」と思い続けてもらえると嬉しいです。