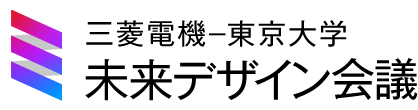研究課題 01 |
サーキュラーエコノミーの実現に向けて
持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座
研究課題 01 |
サーキュラーエコノミーの実現に向けて持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座
「世界の一大研究拠点」を目指す。日本発サーキュラーエコノミーの可能性──三菱電機-東京大学 未来デザイン会議・木下 裕介 × 木見田 康治【前編】

従来の大量生産・大量消費を前提としたものづくりから、近年では欧州を中心に、資源循環を通した価値創出を目指すサーキュラーエコノミーへの移行が大きなトレンドとなっています。
そうした潮流を受けて、2023年10月、三菱電機と東京大学は共同でサーキュラーエコノミーの実現に向けた社会連携講座「持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座」を創設しました。
この講座では日本の製造業の強みを活かして、サーキュラーエコノミーの実現に向けた循環エコシステムの設計と検証、そして実現に向けた課題の抽出と解決策を検討します。三菱電機のさまざまな事業・製品を事例として検証するだけでなく、各ステークホルダーの役割、適切な事業モデル、法規制のあり方などを明らかにしていきます。
サーキュラーエコノミーの実現において重要なのは、「環境負荷の低減」と「企業や個人などすべてのステークホルダーにとっての経済合理性」を両立させること──そう語るのは、社会連携講座を主導する東京大学大学院工学系研究科准教授の木下裕介先生と、特任准教授の木見田康治先生です。本インタビューでは、三菱電機や東京大学だけでなく、製品や資源の循環に関わるさまざまな企業、あるいはさまざまな技術やビジネスモデルなどを組み合わせて日本発のサーキュラーエコノミーの実現を目指す、社会連携講座の全体像についてお伺いしました。
「環境負荷の低減」と「経済合理性」を両立させる
──2023年10月、三菱電機と東京大学が「持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座」を共同で立ち上げています。これにはどのような背景があるのでしょうか?
木見田 この社会連携講座は日本国内にサーキュラーエコノミーの一大研究拠点をつくる試みです。
近年、気候危機や資源問題が迫り来る問題として認識されるようになり、特に製造業では環境負荷を減らすための対応を迫られています。ただ一方で、こうした取り組みは「環境には良いけど経済的利益にはなりづらい」といったイメージを持たれることも少なくありません。サーキュラーエコノミーは「経済」なので、取り組んでいる企業や個人に十分な利益が生まれなければ持続できない。すなわち、「環境負荷の低減」と「企業や個人にとっての経済合理性」を両立させることが肝になります。
そのひとつの仕掛けとして有効なのが、ビジネスモデルの転換、すなわち「お金の流れを変える」ことです。この講座では、東京大学と三菱電機で一緒にそうしたサーキュラーエコノミーを成立させる方法を探求していきたいと考えています。

──たしかに、「環境に良い事業は経済的利益になりづらい」といったイメージは一般に存在するように感じます。その状況を打開するのが、今回の講座のひとつの目標だと理解しました。
木見田 もちろん、本当にできるかはケース・バイ・ケースです。ただ、ビジネスモデルの先行事例はたくさんあります。「シェアリング」はその代表的なものでしょう。
例として、「衣服のシェアリング」サービスが挙げられます。従来の常識であれば、たとえば10人が一人で何着も服を買って所有していましたよね。それを「10人みんなでシェアしましょう」というモデルに転換できれば、衣服をたくさん生産しなくて良くなります。さらに、1着の服をみんなで長く使うことで稼働率が上がり、服1着あたりから得られる価値 を高めて、事業の設計によっては収益も向上させられる。 環境への配慮とビジネス上の利益を両立させられる可能性があるわけです。
──これからの製造業では、ビジネス上の戦略としてサーキュラーエコノミーを取り込んでいく必要性が生まれてくるのではないかと。
木見田 ただし、従来の売り切り型のビジネスとシェアリングサービスを比較して、「どちらが儲かるか?」と言われると難しい部分もあります。しかし、このままサーキュラーエコノミーへと世の中が移行する潮流が加速すれば、今後は売り切り型・使い切り型の製品が規制されるなど、ビジネスが継続していけない世界が近い将来に訪れる可能性があると思います。

サーキュラーエコノミーの「あるべき姿」を描く
──たしかにサーキュラーエコノミーを積極的に推進する欧州では、近年さまざまな規制が強まっていると聞きます。
木下 はい。そうした潮流に対応しなければ、いずれ日本の製造業も立ち行かなくなる可能性がある。言いかえれば、「リスク」への対策としてサーキュラーエコノミーに取り組むべきだという考え方です。
しかし私たちはむしろ、この潮流を「リスク」ではなく、変革の「機会」と捉えられれば良いと思っています。サーキュラーエコノミーの「資源を循環させる」というコンセプトから新しい価値を生み出す方法を考えたり、事業モデルを変革したりすることで、将来のものづくり企業のあり方を捉えなおす機会が生まれると思うんです。
そのためには、サーキュラーエコノミーを“ツール”として使っても良いと思います。例えば「サブスクリプション」「レンタル」「リース」など、ビジネスモデルの事例は豊富に存在しています。こういった、既存事例のいくつかのパターンを掛け合わせることで、新しいビジネスの発想の種を生み出せる「モーフォロジカル分析」のような手法もあります。知識があれば最初のステップは踏み出しやすい環境が整ってきていると思います。

──まずは“ツール”を活用して、企業が自社のビジネスをいかに変えられるかを考えてみることが有効なのではないか、というわけですね。
木下 しかし一方で、こうした“How”から考え始めるだけでは中途半端に終わってしまいがちです。サーキュラーエコノミーを推進し、ビジネスモデルを根底から転換するのは、ひとつの企業の力だけでは難しいからです。
まずは、「そもそもサーキュラーエコノミーを通じて何を実現したいのか」を考える。そのビジョンをもとに、関係者たちの合意を得ながら推進していく。そうした逆算的な思考も同時にやっていかなければ、製品のライフサイクル全体の循環をうまく回すためのエコシステムを生み出せません。
木見田 そこで社会連携講座では、参加者と一緒に「なぜサーキュラーエコノミーを実現したいのか」という問題設定から考えていく予定です。
この講座には三菱電機の研究者だけでなく、事業部の方にもご参加いただく想定です。決められた研究テーマに沿ってただ進めるだけでなく、そうした事業部のメンバーの方々にヒアリングして具体的なニーズや課題を把握した上で、研究計画やテーマの中に落とし込んでいく想定です。
木下 例えば社会連携講座のワークショップでは、具体的な製品を対象にして、「サーキュラーエコノミーがなぜいま必要なのか」を議論してもらっています。現在の課題は何か、それを解決するにはどのような研究をすればいいのかを考えてもらう。そのグループワークの過程で、みなさんも「サーキュラーエコノミーをやったほうがいいよね」ではなく「やらないと駄目だよね」という動機を持つようになっていただくことが多いと感じます。

日本発・サーキュラーエコノミーの世界的な研究拠点へ
──この社会連携講座では最終的にどのような状態を目指しているのでしょうか?
木見田 私としては、「世界一」と呼ばれても遜色ない研究拠点を3年以内につくりたいと思っています。野心的な目標だと感じられるかもしれませんが、これは現実的に可能という認識です。というのも、やはり日本には長い時間かけて製造業の現場で培われた、独自のものづくりの経験と技術力があるからです。
──とはいえ、サーキュラーエコノミーは、やはり先ほどお話していたように欧州が主流だというイメージがあります。
木見田 たしかにこの概念自体は欧州から入ってきているため、身近なものではないと感じている人も多いと思います。しかし、日本にはこれまでのものづくりにおいて築き上げてきた洗練されたインフラや技術があります。そして、日本にはサーキュラーエコノミーの分野で活躍されている、欧州に負けない優秀な研究者がたくさんいる。
その知見を活かして、サーキュラーエコノミー時代に向けて技術やビジネスモデルを変革していけば、日本のものづくりの強みが活かされた、独自のサーキュラーエコノミーのモデルが生まれると思っています。そして、それは世界に向けて「打って出る」ことができるものになると思うんです。
──日本の製造業が培ってきた強みは、サーキュラーエコノミーの時代だからこそ活きるのではないかと。そして、今回の社会連携講座はその起点となる存在だと考えているんですね。
木見田 私はサーキュラーエコノミーの一大拠点と言われるデンマーク工科大学に所属していたのですが、そこでは大学を中心にこの分野が発展していました。世界各国から優秀な研究者たちが集まり、多くの企業が大学の動向をウォッチしながらサーキュラーエコノミーの実装を試行錯誤している。だから、東大もそうした拠点のひとつとして旗を立てられれば、世界各国から研究者が集まり、企業とともに発展できると思うんです。
また、海外の研究者は日本のメーカーの動向が気になっていると感じます。私も「日本はいまどうなっているの?」「これからどうしていくの?」と質問されることが多いんです。だから、日本有数の大企業である三菱電機が取り組みを始めるだけで興味を持つ 研究者は世界中にいるはずですし、そこで先進的なモデルを打ち立てられれば、「ここで学びたい」「一緒にやりたい」という人が集まってくるポテンシャルが十分にあると思っています。